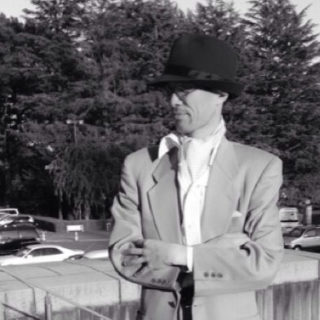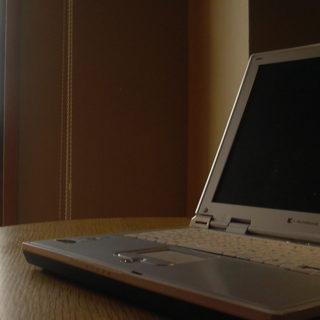日本最北端の地・宗谷岬から、オホーツク海に沿って北海道を南へ進んでいきます。
能取湖

宗谷岬から休憩をはさみつつ、およそ5時間かけて能取湖(のとろこ)付近までやってきました。
能取湖は、網走市の郊外にある、日本で14番目に大きな湖で海水の湖です。
1973年に護岸工事がおこなわれるまでは、海水と淡水が入り交じる汽水湖でした。
「能取」の名前は「岬の場所」という意味のアイヌ語「ノッオロ」からきており、これは本来湖の北東にある能取岬のことを指します。
濃霧の根北峠
さらに車を進め、オホーツク総合振興局(旧網走支庁)と根室振興局(旧根室支庁)の境界となる根北峠まで差し掛かりますが…

濃霧に見舞われました。

峠道なので、道路脇にもまだ多くの雪が残っています。記憶に間違いがなければ、多少の雪も降っていたかと思います。能取湖ではぬるく感じた空気も、根北峠では冷たく感じます。
この根北峠は、知床半島の付け根を横断する峠で、積雪期も踏破できる、北見国と根室国とを結ぶルートとして、1885年に開削されたのが始まりです。
野付半島に寄り道

峠を下りしばらく走ると、野付湾に到着します。
野付湾は、野付半島に囲まれた部分にできた湾です。1~2mという浅い水深の湾内で行なわれるホッカイシマエビの打瀬網漁は、風物詩にもなっています。
また野付半島は、独特な細長い地形をしています。これは、海流によって運ばれてきた砂が積もってできた、砂嘴(さし)と呼ばれる地形です。

海側を見ると、向こうに島を見ることができます。国後島の螻向崎(ケムライざき)で、野付半島とは20km程度離れています。
野付半島は、江戸時代後期にキラクという集落があり、この野付半島から国後島へ渡る交通の要所として栄えていました。今でもその名残を見ることができますが、浸食により多くが海へ沈んでしまっています。
夕方、根釧台地に到着!

根釧台地の田園風景です。この写真を撮影した時間は、記録では18時の少し前ごろでした。
すでに日没の時間にもかかわらず、この日でいちばん暖かな空気を感じたのを覚えています。
雪の降るサロベツ原野で朝を迎え、冷たい雨交じりの宗谷岬に立ち寄り、オホーツク海を南下し、生ぬるい風を受けながら網走を走り、まだ雪が残る肌寒い根北峠を越え、そして、野付半島や根釧台地で太陽の暖かさを感じながら、北海道を南下してきました。
同じ北海道でも、まったく違う顔を持っているなと、気温の違いだけでもよく知ることのできる一日でした。
2003.04.30
投稿者プロフィール
最新の投稿
 クイズ2024.01.26クイズ【略称】
クイズ2024.01.26クイズ【略称】 クイズ2024.01.14クイズ【神話・伝説】
クイズ2024.01.14クイズ【神話・伝説】 ひとりごと2023.07.09【祝】おかげさまでサイト開設20周年を迎えました!
ひとりごと2023.07.09【祝】おかげさまでサイト開設20周年を迎えました! クイズ2023.06.19クイズ【格言・名言】
クイズ2023.06.19クイズ【格言・名言】