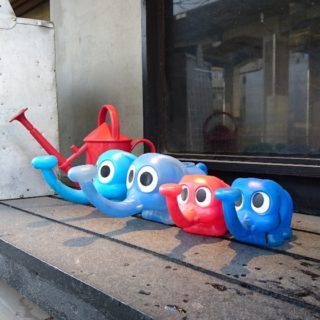渋谷・原宿から次の目的地を目指しますが、その前に、ちょっとだけ御茶ノ水に寄り道をしたようです。
御茶ノ水の“水”は、徳川家の御用達だった
「御茶ノ水」という地名は、この地にあった金峰山高林寺というお寺の湧き水を使ったから作られたお茶から来ています。
鷹狩りの帰りに立ち寄った、江戸幕府2代将軍徳川秀忠が、この寺の湧き水を使って作られたお茶を飲んで以来、徳川家御用達の水になったことから、この地が「御茶ノ水」と名付けられました。
この地域で時折見られる「茗溪(めいけい)」という名称も、御茶ノ水の雅称を由来としています。
御茶ノ水に架かる「聖橋」

御茶ノ水の神田川に架かる聖橋です。関東大震災の震災復興橋梁として、1927年に架けられました。
橋の両側にある、湯島聖堂とニコライ堂の、2つの聖堂を結ぶ橋であることから「聖橋」という名前が付けられました。
設計は、後に日本武道館や京都タワービルを手がけることになる山田守です。
この2日前、西新宿のパークハイアット東京にチェックインしたあとにもここを訪れています。

その時の写真です。
聖橋のアーチの向こうに見える平らな橋は東京メトロ丸ノ内線です。区間でいうと、御茶ノ水駅と淡路町駅の間になります。
さらに奥のネオンが点灯しているビル街が秋葉原電気街です。
橋の脇には、1904年12月31日に開業したJR中央線の御茶ノ水駅があります。現在の駅舎は、1932年の総武本線乗り入れ時に改築された2代目駅舎で、万世橋にあった交通博物館や戦災復興の東京駅、東京駅八重洲口など多くの国鉄駅舎を手がけた伊藤滋によるものです。駅舎に待合室がなく、やってきた乗客をそのままホームへ流す設計の駅はこの駅が初めてだそうです。
2002.11.02
投稿者プロフィール
最新の投稿
 クイズ2024.01.26クイズ【略称】
クイズ2024.01.26クイズ【略称】 クイズ2024.01.14クイズ【神話・伝説】
クイズ2024.01.14クイズ【神話・伝説】 ひとりごと2023.07.09【祝】おかげさまでサイト開設20周年を迎えました!
ひとりごと2023.07.09【祝】おかげさまでサイト開設20周年を迎えました! クイズ2023.06.19クイズ【格言・名言】
クイズ2023.06.19クイズ【格言・名言】