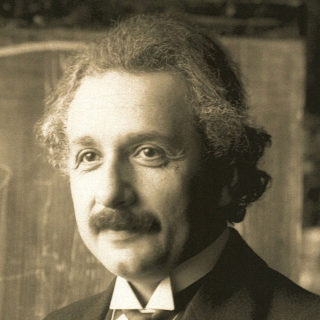浜松に到着
新幹線に乗ってやってきたのは静岡県浜松市です。
市の南部には有名な浜名湖があり、東海地方では愛知県名古屋市に次ぐ人口の多い都市です。2007年4月1日には政令指定都市に指定されました。

こちらは1994年に完成した、浜松駅前に建つアクトシティです。到着した日はここには訪れず、友人と会い夕食にうな重を食べたのを覚えています。
浜松のウナギ養殖の歴史
浜松といえばウナギの養殖で有名ですが、これは服部倉治郎という人物が1900年に浜名湖がウナギの養殖に適していると判断し、現在の浜松市西区舞阪町に約8町歩の養鰻池を造ったのが始まりです。
その後村松啓次郎という人物が浜名湖のウナギ養殖を発展させ、服部が用いてきたクロコウナギでは生産量に限界があるとしシロコウナギから育てる方法を1971年に確立しました。また村松はビニールハウスによる加温養殖法を考案しました。
浜松は産業が盛んな街
また浜松は産業が盛んな地域で、本田技研工業創業の地でスズキやヤマハの本社所在地がありヤマハや河合といった楽器の一大生産地でもあります。
1972年に大阪で創業したローランドも、2005年より浜松に本社を移転しています。さらに浜松高等工業学校(現在の静岡大学工学部、工学部のキャンパスは現在も浜松にある)の助教授だった高柳健次郎は、1926年にこの街で世界で初めてテレビジョンを発明し、浜松出身の天野浩は、青色LEDを開発した功績が認められ、2014年にノーベル物理学賞を受賞しています。
浜松は楽器の一大生産地ということもあり、駅近くのアクトシティ内には日本で唯一の公立の楽器博物館である浜松市楽器博物館があります。1995年に開業しました。浜松到着の翌日午前に、この博物館を訪れています。
アクトシティ浜松

1994年に完成したアクトシティ浜松は、旧国鉄の貨物駅跡地に1994年に建てられました。
浜松が音楽の街であることを意識し、外観はハーモニカをモチーフとしています。
同施設内にそびえ立つアクトタワーは212.77mの高さがあり、これは1998年に名古屋市にJRセントラルタワーズが完成するまで、東海地方で最も高いビルでした。静岡県内では、現在でも最も高い建築です。

45階の展望回廊から見た遠州灘です。
この地域は、浜名湖がかつての都(大和国)から見て遠くにある淡海(あわうみ=湖)であり、都から近い琵琶湖(近江)と比べて遠江国(とおとうみのくに)と呼ばれました。そのため、この近辺の海は「遠州灘」と名付けられました。
写真奥に広がる海が遠州灘です。ちなみに左に見える大きな道路は広小路通で、右に見える川は馬込川(まごめがわ)です。
再び新幹線に乗って富士山を見ます

あっという間に浜松から旅立つ時間になりました。
この時乗った新幹線は700系車両でした。0系車両や100系車両の置き換えを目的として製造された車両です。この電車に乗って東京まで戻ります。

前日の、浜松へ行くときに乗車した新幹線から見た富士山です。
この時は山頂部が雲で覆われていましたが、帰りはどうでしょう。

再び新幹線車内から撮影した富士山です。前日の、浜松へ行く時に乗車した新幹線で見た富士山と比べ、雲があまりかかっていません。

富士山のふもとに広がる富士市の街並みも、クリアに見えました。
写真では、富士山の稜線の右側にちょっとだけ盛り上がっている部分がありますが、これは「小富士」と呼ばれ、標高が1979mあります。
おおよそ10-20万年前、この地に最初にできた火山が現在の小富士で、地質学的には小御嶽(こみたけ)火山といいます。その後噴火を繰り返し約1万年前に現在の富士山(新富士火山)ができました。


富士山の手前に別な山が写りこんでいますが、こちらは標高1504mの愛鷹山いう山で、この山を通り過ぎると三島市へ入ります。
東京駅に到着

新幹線は東京駅に到着し、この度の浜松旅行は完結しました。

隣には200系200番台もしくは2000番台の車両が停車していました。東北・上越新幹線用に製造され、このタイプの車両は1987年から2005年ごろまで運用されていた車両です。
東北・上越新幹線は東海道新幹線とは違い、多くの区間が豪雪地帯であるため、雪の対策が多くとられていることが特徴です。
この日はまた浜松へ行く前に会った友人と再度会ったあと、また別な友人と会い、その方のお宅に泊らせていただきました。
2002.11.03
投稿者プロフィール
最新の投稿
 クイズ2025.04.21サザエさん一家で唯一同じ名前の駅があるのは誰?~【日本の駅名】のクイズ
クイズ2025.04.21サザエさん一家で唯一同じ名前の駅があるのは誰?~【日本の駅名】のクイズ クイズ2025.02.07「朝」という名前の単位がある?ロバが基準の単位って?~【単位】のクイズ
クイズ2025.02.07「朝」という名前の単位がある?ロバが基準の単位って?~【単位】のクイズ クイズ2025.01.29地球は太陽系の惑星で何番目に大きい?~【宇宙と星空】のクイズ
クイズ2025.01.29地球は太陽系の惑星で何番目に大きい?~【宇宙と星空】のクイズ クイズ2024.01.26アンデスメロンの「アンデス」って?~【略語】のクイズ
クイズ2024.01.26アンデスメロンの「アンデス」って?~【略語】のクイズ