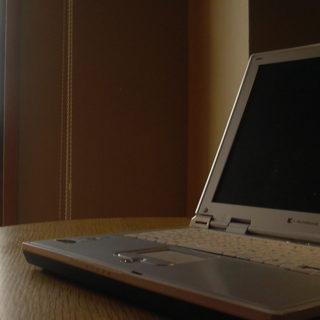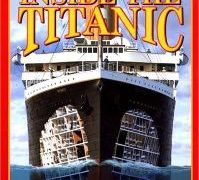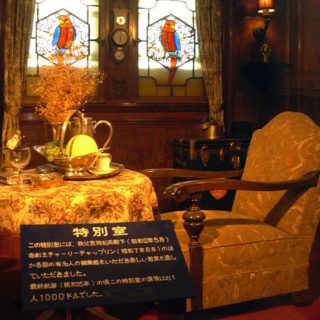「方程式」は、中学校1年生の数学で初めてその名前で勉強します。
その時はあまり意識していなかったかもしれませんが、よく考えると方程式の「方程」ってなんだろう?と疑問に思いませんか?
今回はその謎を解いていきたいと思います。
「方程」という言葉は昔の中国の数学書から
実は「方程式」という言葉は、紀元前1世紀から紀元後2世紀に書かれたと考えられている中国の数学書『九章算術』から採られています。
題名のとおり全部で9章あり、その中に246の問題が収められた、問題集形式の数学書です。唐の時代には教科書としても使われました。
章ごとの中身を簡単に見てみましょう。
- 方田:38問。田畑の面積求める計算。分数の計算や図形の面積を求める計算、ユークリッド互除法について記されています。
- 粟米:46問。交換比率が違う商品の物々交換する際に必要な計算。比例の計算や不定方程式について記されています。
- 衰分:20問。納税や財産配分、利息の計算。数列の計算などが使われる場合もあります。
- 少広:24問。土地の測量で必要な計算について。平方根や立方根、辺の長さを求める計算が記されています。
- 商功:28問。土木工事や労働者の数、土砂の体積を求める計算が記されています。
- 均輸:28問。田畑から徴収した税を運ぶのに必要な計算。距離や日程、運送費に関係する計算が記されています。
- 盈不足:20問。いわゆる鶴亀算について。過不足を求める計算が記されています。
- 方程:18問。多元一次方程式の計算方法について。そのための負の数の計算のきまりについても記されています。
- 句股:24問。測量に必要な計算。三平方の定理(ピタゴラスの定理)について記されています。
第8章が「方程」という題になっていて、そこから「方程式」という言葉が生まれました。「方」は比べること、「程」は大きさや量という意味です。
投稿者プロフィール
最新の投稿
 クイズ2024.01.26クイズ【略称】
クイズ2024.01.26クイズ【略称】 クイズ2024.01.14クイズ【神話・伝説】
クイズ2024.01.14クイズ【神話・伝説】 ひとりごと2023.07.09【祝】おかげさまでサイト開設20周年を迎えました!
ひとりごと2023.07.09【祝】おかげさまでサイト開設20周年を迎えました! クイズ2023.06.19クイズ【格言・名言】
クイズ2023.06.19クイズ【格言・名言】